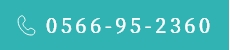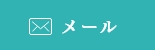ブリッジの特徴

ブリッジの特徴は、硬いものもきちんと噛めることです。ただし、歯がない部分の両側の歯を削り、その2本を土台として歯を支えるため、土台となる2本の歯には少しずつ負荷がかかります。そして、もし被せ物の種類が金属の場合は、更にその負担が大きくなるので、歯が削れてなくなる原因につながります。
ブリッジが適しているケースと適さないケース
ブリッジはものがしっかり噛めて、保険も適用される治療などメリットが多い治療法ですが、症状によっては適さない症例もあります。
| 適しているケース | 適していないケース |
|---|---|
|
|
ブリッジのメリットとデメリット
命に係わることはほとんどないですが、歯科治療をする前にしっかりとブリッジのメリットとデメリットを確認しましょう。
ブリッジのメリット
保険適用で治療費がお手頃?
ブリッジは、保険が適用されるため入れ歯やインプラント治療に比べて治療費の負担が少ないです。ただし、治療に使用する金属は5年ほどで劣化し始めるので生涯治療にかかる費用として考えた場合は、高くなる場合もあります。特に甘い物など砂糖を好んで食べる人は、金属の劣化を早めてしまいます。また、歯間ブラシの習慣がない方や、定期的な検診に行かない方の場合は、ブリッジ周りのケアが十分にできないためブリッジは不向きです。
インプラントや入れ歯の治療よりも治療期間が短い

インプラント治療は最低でも半年程度の治療期間がかかり、入れ歯は、噛み心地や使用感が良くなるまでの調整に時間がかかる場合があります。ブリッジは、型を取ってから比較的すぐにパーツが出来上がり、それを被せるだけなので治療期間が短いです。
ブリッジのデメリット
歯を削らなければいけない
歯がないところをブリッジで補修するためには、健康な歯であっても両側の2本の歯を削らなければいけません。また、ブリッジは5年程度で劣化するので、再治療をする時は更に歯を削る必要があります。歯は再生されないので、削れば削るほど歯がなくなってしまうことがブリッジのデメリットといえるでしょう。
耐久性が短い
ブリッジの耐久性は5年~8年ほどです。毎日の歯磨きが不十分であったり、メンテナンスを受けていない場合は更に耐久性が短くなる場合もあります。また、劣化をすると再び治療をしなければいけないので、手間や治療費、体への負担がかかります。
保険診療と自費診療におけるブリッジの違い
ブリッジの治療には、国民健康保険が適用のものと適用外のものがあります。治療費だけを考えれば、保険診療の治療が有効ですが自費診療のメリットなど、どのような違いがあるかをわかりやすく表にまとめて説明します。
| 保険診療 | 自費診療 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 〇 適用 | × 適用外 |
| 治療費 | 〇 お手頃 | × 保険が適用されないので実費 |
| 素材 | × 決められた素材から作る | 〇 患者さんの好みや症状によって選べる |
| 治療工程 | × 保険適用で定められた工程を守る必要がある | 〇 必要ない治療を省いたり、丁寧に時間をかけて治療をするなど自由にアレンジできる。歯茎の形をかえて義歯と見分けがつかないように治療をすることもできます。 |
| 汚れ | × 限られた素材でつくるので、汚れが付きやすい | 〇 好きな素材を選べるので汚れが付きにくい |
| 噛みやすさ | × 限られた素材と決められた治療工程で作るので、噛み心地は自費診療に比べて劣る | 〇 時間をかけて調整するので、噛んだ時の違和感がほぼない |
| 耐久性 | × 5年~8年 | 〇 保険のブリッジの2倍~3倍 |
メンテナンスについて

ブリッジ部分は糸ようじが使えません。そのため、丁寧に歯磨きをした後に、歯間ブラシを使って磨き残しをきれいに落とす必要があります。虫歯や歯周病の原因にもなるので、甘いものはできる限り控えましょう。
また、丁寧に歯を磨いているつもりでもセルフケアには限界があるため、定期的に歯科医院でメンテナンスを受診してください。頻度は3ヵ月に一回程度が一般的ですが、虫歯になりやすい方や歯磨きの磨き残しがある方などは1~2ヵ月に一回お願いすることもあります。歯科検診をした際に、必要と判断した場合は歯石や歯垢の除去をします。
その後専用の医療器具を使って歯茎とブリッジの隙間をきれいにします。このメンテナンスは金属だけでなくセラミックを使った場合でも必須です。なお、歯茎が腫れてからやると痛みを感じることがあるので、腫れる前からメンテナンスを受診することを心がけてください。
ブリッジの治療の流れ
歯がない部分をブリッジで治療をする場合の、治療の流れをご紹介します。

1初診
歯科医師が問診票の内容と視診をもとにカウンセリングをします。

2事前処置の確認/治療
一つ一つ丁寧に虫歯や歯周病などがないかを確認します。そして事前に処置が必要な場合は、歯の治療を施します。

3歯茎の確認/治療
健康な歯茎でないと、せっかく治療をしても歯が安定しない場合があります。そのため、歯茎の状態を確認し、必要な場合は改善を図る治療をします。

4治療開始
歯茎が引き締まった状態になったら、ブリッジの治療を開始。失った歯の両側の歯を削って、ブリッジを被せるための処置をします。この時に、必要な場合は神経の処置を施します。なお、神経の処置にかかる分だけ治療回数が多くなることはご了承ください。
5型取り
印象材を使って歯の型取りをします。仕上がりまでの時間は保険適用の場合で約一週間、自費診療の場合はより丁寧に調整をしながら作製をするので更に時間がかかる場合があります。詳しくは歯科医師にご確認ください。

6ブリッジの取り付け
ブリッジが完成したら装着して、違和感や噛み心地などを確認します。気になることがあればご遠慮なく歯科医師にお申し付けください。調整が終了したら治療完了です。
ブリッジの費用
自費の場合
| 印象(型取り) | 3,300円(税込) |
|---|---|
| 通常の一歯欠損の治療費(神経がある場合) | 267,300円~421,300円(税込) |
※本数によって費用は変動します。